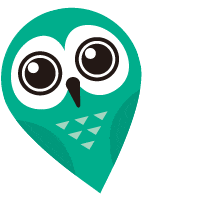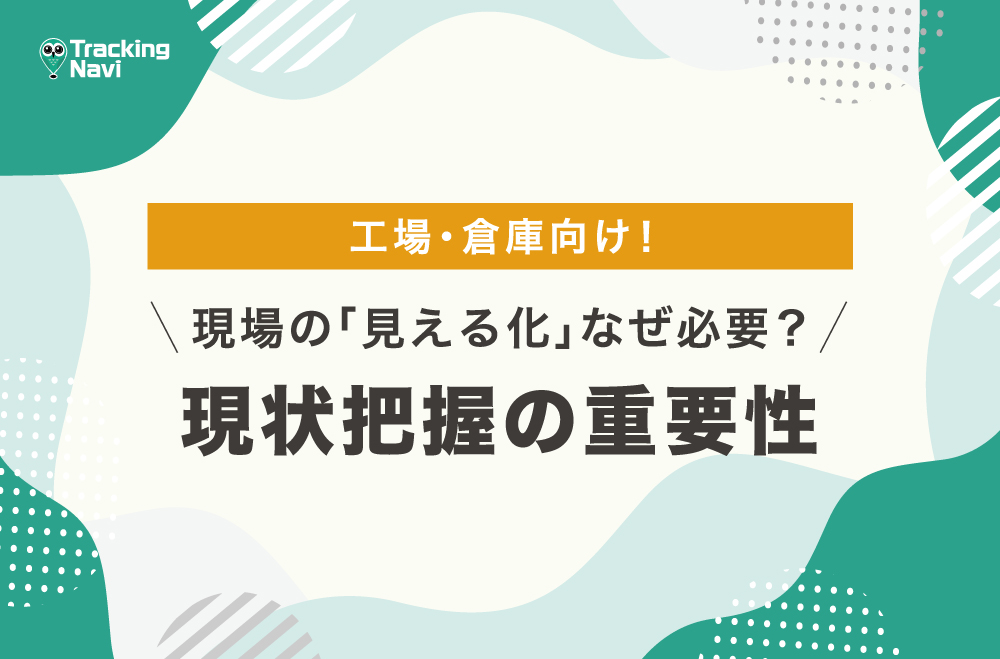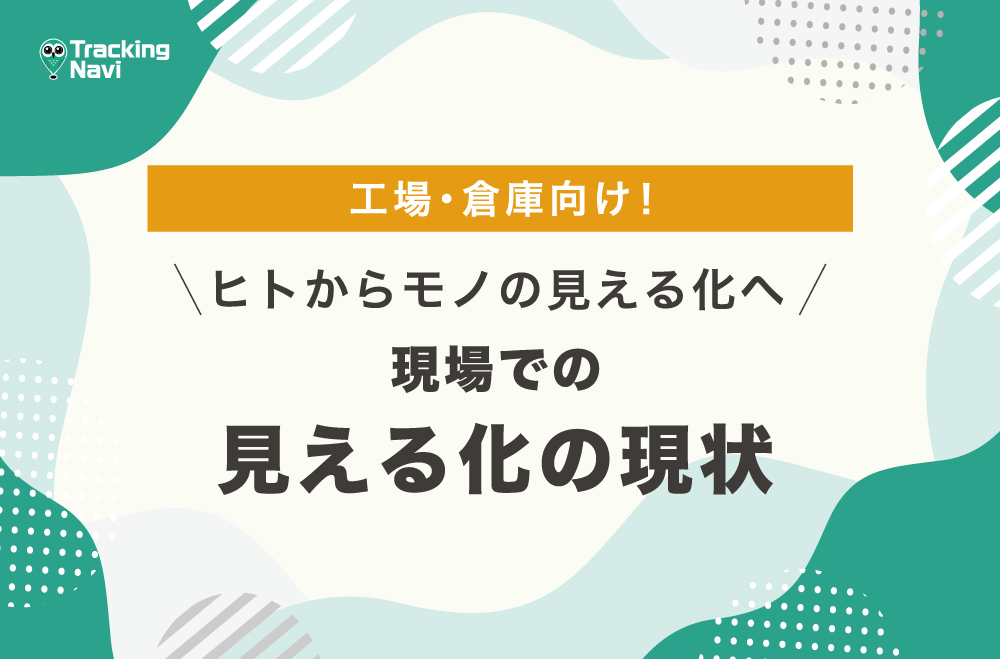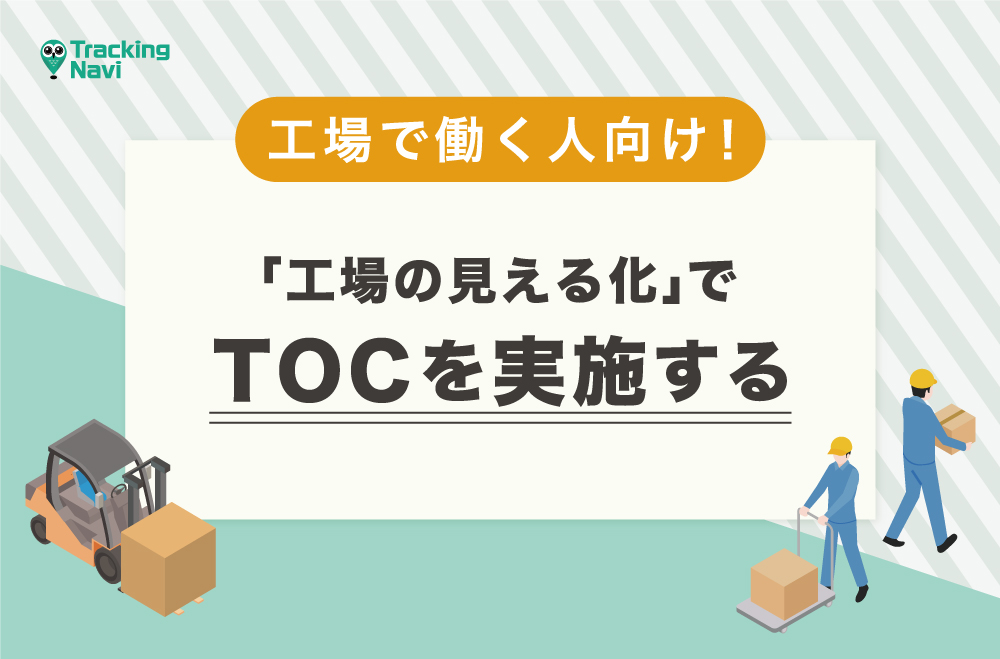コラム
Column

2022.07.11
「工場 効率化」の目的と効率化のために今できること
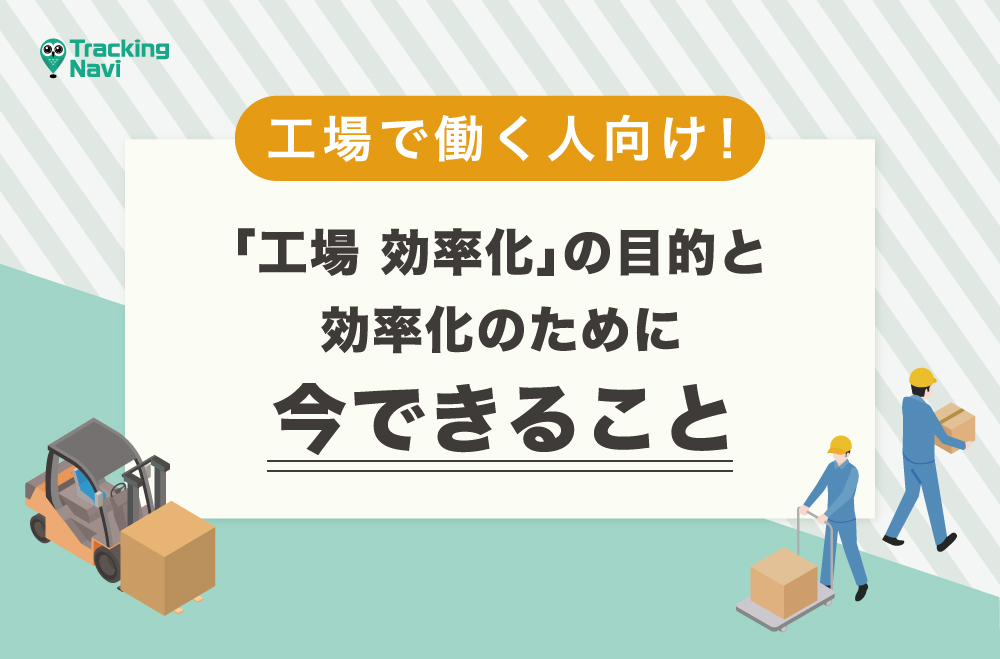
工場を効率化する目的は、当たり前ですが収益をあげることです。企業においては、投資利益率、つまり投資額に対してどれだけ利益を生み出しているか、が成功しているかどうかをみる一つの指標になっています。 投資利益率を向上させるためには、より少ない投資でより大きな利益をあげられるようにすることが必要となります。
一方で、収益を得るためには、作った製品が売れなければなりません。
そのためには、世の中のニーズにあった製品を作る必要があります。
本コラムでは、改善の方向性や時代のニーズに沿った生産方式の変遷を見ていきたいと思います。
目次
工場の効率化とは
世の中にはさまざまな業種がありますが、製造業では「企画・製造・物流・販売・マーケティング・サービス」といった業務が連携することで、初めて顧客に価値を届けることができ、収益を得ることができます。
工場での生産が完了していても、製品が顧客に販売されていなければ収益になりません。
こういった業務プロセス全体の効率が、投下資金の回収効率として現れるのです。
これらの業務のうち、製造プロセスの効率化は、製造業の生産管理・生産技術が担うもっとも重要な役割です。
効率をあげるとは、少ない投資や費用でより大きなリターンを得られるよう、業務を改善するということです。
製造プロセスにおいては、より少ない労働時間で生産する、在庫を抱えすぎない、注文を受けてから販売までのスループットをあげる、といった改善を行うということになります。
業務改善の方向性=資金需要の削減(資金効率)
生産管理・生産技術の「改善」によって、より少ない投下資本で高い収益をあげることが出来るようになります。 つまり「資金需要の削減」を図り、利益率を上げることで「資金効率」が上がるのです。そのために有効な手法が、「ムダ・ムラ・ムリ」の排除です。
製造業では、手工業の時代から産業革命を迎えた後も、絶えず生産管理・生産技術により「改善」を重ねてきています。
大量生産の時代に入り、かつ株式会社の形態となると、「資金運用」の考え方、即ち「配当金」を稼ぐ考え方が広まり、より作業の「ムリ・ムラ・ムダ」を生産管理・生産技術で排除する方向性が求められてきました。
ロット生産から多品種少量生産
手工業の時代を経て、やがて蒸気機関が発明されると、動力で動く工作機械によって大きく効率が上がります。その後、動力源が電力に変わることでさらに生産性が上がりますが、一定の数量をまとめて生産するロット生産方式は変わりませんでした。
しかし、世界の中で日本企業だけはロット生産の大きなムダに早くから気付き、そのムダを取り除くため、苦労を重ねながらも生産方式を「多品種少量生産」に移行していきます。
その効果は「資金効率」を1千倍にしたと言えるほど高く、日本の高度成長期の資金源になり、日本を世界の経済大国にのし上げていきました。
アメリカとの貿易戦争の時代、「日本式多品種少量生産方式」は「リーン生産方式」との呼び名で世界に紹介されました。
するとその資金効率の高さに反対する者などおらず、世界の量産製造業で「日本式多品種少量生産方式」を採用していない工場がないほど普及してしまいました。
この結果、日本の製造業は相対的に優位性を失い、いまや日本企業が切り札を持たない状態となっています。
ライン生産からセル生産方式へ(通称:屋台)
ベルトコンベアによる流れ作業生産を基本とすると、連続する作業の工数が均一でない場合は、負荷の大きな工程(ボトルネック)で生産量が制限されてしまいます。
「多品種少量生産」の一種の「混流生産」においても工数の均一化は難しく、生産管理・生産技術における大きな悩みでした。
そこで考え出されたのが、工程間の工数差を問題化しない「セル生産方式」、通称:屋台です。短い生産ラインを何本も作り、市場の需要に合わせて生産ラインの本数を増減させるなど、生産調整が出来る方法が編み出されています。
例えば建設車両では、乗用車に比べ1機種あたりの生産台数が少なく、反対に機種の種類が多いため、セル生産方式の「混流生産」が向いています。
しかし、たくさんの車種を「混流生産」するためには、組み立て人員は多くの車種の組み立てに携わらねばならず、熟練工の養成が必要です。
ところが、熟練組立工の養成には時間がかかるため、生産管理・生産技術にとっての課題となっていました。
デジタル屋台
上述の通り、セル生産方式が採用されると、多種類の組み立て作業を行える多能工の必要性が出てきました。しかし、その養成には多くの年数が必要です。
そこで考え出されたのがITを活用した「デジタル屋台」です。
「デジタル屋台」でのIT活用は、事務作業の自動化や機械の自動制御化にとどまらず、マニュアルのデジタル化など幅広いものになっています。
熟練工の作業を記した作業マニュアルを現場のコンピュータで表示し、その画面と音声で指示を受けた非熟練労働者がそのマニュアルに沿って組み立てる。
こういったIT活用によって、熟練工が長年かけて覚えた組み立てを、非熟練労働者が1週間ほどで出来るようになった工場もあります。
もちろん、ミスがあった時には自動的にストップさせる機能を作り、フォローを受けながら作業できます。
こういった「デジタル屋台」の登場は、生産管理・生産技術にとって大きな革新でした。
今後はロボット化やAIによるリアルタイム作業監視が普及していくと予想されますが、これらによってますます生産リードタイムが短くなり、資金効率が上がることになります。 つまり、混流生産によって、材料仕入れから製品納入、現金化までのリードタイムが劇的に短縮され、運転資金を大幅に減らすことができるのです。
ネット時代の第4産業革命
「蒸気機関・電気・コンピュータ」の登場に伴い3度の革命を迎えた産業界でしたが、現在ネット時代を迎え、新たな産業革命が起きつつあります。
ネット通販です。
自動車業界なども例外ではなく、オーダーメイドのように多種類のオプションをユーザーが選択してネットで注文し、メーカーが即座に生産して納車できるシステムの構築が進んでいます。
すでにドイツ企業では、100ほどのオプションをネット上で選択して、自分だけの1台をネットで注文すると、2週間程度で生産して納車するというシステムが実験されています。
「世界の生産拠点のどこで生産するのが適切なのか?」もAIが判断して生産を振り分け、短期間での生産から納車を目指しています。
これにより、ますます材料発注から製造、納車して資金回収するリードタイムが短くなり、資金の回転が速くなって資金効率が上がっていくことになります。
まとめ:「工場 効率化」の目的と効率化のために今できること
企業の資金効率の向上を求める動きは、これからも変わらず続いていくでしょう。
本コラムでこれまで見てきたように、生産技術は時代を追うごとに進化を続けています。その背景には、消費者のニーズが多様化してきたということが挙げられます。
進化する技術をうまく取り込みながら、生産形態も継続的に見直していく必要があります。
需要が変動すると、それにともなって生産対象の商品、作業工程、作業者数などが変化します。時には生産方式を適したものに変更する必要もあります。
こういった変化に柔軟に対応するには、まず、効率が悪化していないか、採算がとれているか、といった「現状を常に把握」できるようにしておく必要があります。
現状の効率が把握できていなければ、何かを変更した時に、効率が上がったのか下がったのかを知ることもできません。
例えば、作業者の工程ごとの作業時間や作業者の動線などをデータとして記録しておき、変更の前後で比較することで、効率に対する影響をデータに基づいて客観的に示すことができます。
まずは、現状を正しく把握することから、工場の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。
お電話でのお問い合わせ
【東京】03-3257-1141
【大阪】06-6442-1329
受付時間:
平日9:00 - 17:00
(土日祝日、年末年始を除く)